![]()
| 日 時 | 平成18年10月 20日 | |
| 午前の部
|
「長嶺プレイパーク」から考えること ○開講式 ○わらべうたゲーム ○長嶺プレイパークについて(藤木さんはじめみなさん) |
|
| 午後の部 | 「地域とは?」ワークショッププログラム ○やまなみ保育園でワークショップ ■ステップ1 話題提供(浜崎先生、やまなみ保育園園長山崎先生) ■ステップ2 プレイパークの感想でお隣さん紹介 ■ステップ3 プレイパークみたいなのができるためには!? ■ステップ4 地域ぐるみ子育て支援のためのコーディネーターの役割とは? ■ステップ5 各班発表 ■ステップ6 全体での意見交換 |
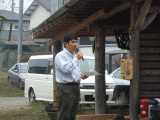 |
 |
 |
 |
 |
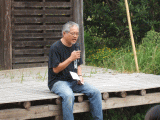 |
 |
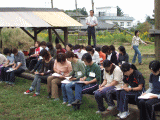 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
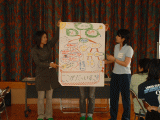 |
| 第3回 コーディネーター研修会報告 |
|
| 於: 長嶺プレイパーク・やまなみ保育園 | |
| 『長嶺プレイパークとは』 | |
| 午前:「長嶺・プレイパークにて現地研修会」 オープニング・『わらべ歌遊びの効能』 敬愛保育園の森川 聡美先生の指導の下、わらべ歌を歌いながらの遊びを参加者に紹介していただきました。研修者の多少ぎこちない雰囲気が一気に柔らかくなり、「遊び」は知らない者同士を打ち解けさせやすい、ということがここでも再認識されました。歌う、体を動かす、人と触れ合う、考える・・・色々な要素が絡み合うように考えられていて、研修者の勉強と共に親睦が進みました。 そして最後は、グループ作りのわらべ遊びで出来上がったグループを、「そのグループが、午後のワークショップのグループです」という森川先生の見事な締めで終了となりました。 続いて今回の研修地である「長嶺プレイパーク」を支えてくださっている、地元主要なメンバーの方に、お忙しい中お越しを頂き、研修者に向けてお話しをいただきました。 『長嶺・プレイパークメンバーより』 最初に、実質的な長嶺・プレイパークの創始者である、藤木 一冶・長嶺校区まちづくり会会長から話をいただきました。続いて地元自治会の井上会長を筆頭にして多くの方々に、プレイパークの始まりや想い、プレイパークに携わるようになって感じること、集える場所があることの喜び等、それぞれの立場で語っていただきました。 びっくりしたのは、話し始めると、次から次に地元の方がお越しになり、次々とマイクが渡っていった事です。終わりかな、と思うと次の方がいらっしゃって、熱心にメモを取ってフト顔を上げると立っているメンバーの数が増えていたり・・・と。一体何人いるんだ!?という感じでした。 『共同作業の賜物』 話を聞いていて総合的に思うことは、今の時代は、大人が関わる事が『子ども達の精神的成長』につながりやすいのだな、という事でした。 プレイパークの建築物(トイレ・シンボルタワー・小屋・炭小屋など)のほとんどは、大人と子どもの共同作業で作られています。その殆どが大人と子どもの共同作業の賜物です。少しでも子どもに携わらせようという姿勢が、メンバーの話と実際の建築物見栄えの端々に見えてきます。 しかし、その結果のエピソードとして、殆ど子ども達だけで小屋を建てたり、悪さをして怒られても自分達で大人に謝りに来る事が出来たり・・・、と今時珍しい!?こういう話が聞けました。 集団で何かをするというときは、それ相当の精神的発達が求められます。お互いがお互いの立場を分かり合いながら認め合いながら、結果として立場を超えて楽しみあうという感覚でしょうか。そして、子ども達のそういった感覚の練磨には、そのめんどくさいと思われる共同作業が一番である、ということが長嶺・プレイパークのスタッフの話から見えてきます。第1回目の研修場所であった、植木町・「ばあちゃんち」の基本スタンスの中にもその精神があったように思います。 『人は人で育つ』 現代は治安状況の不安定化や車事情の危険性等から、子ども達の群れて遊ぶ環境(共同作業の場)は激減しました。その結果、家族だけではなく、子どもの核化が進みました。更にそれを満たすようにしてインターネットや家庭用ゲーム機が普及した為、あえて友達を作ったり、求める必要性も無くなりつつあるようにも思えます。 主要メンバーの一人である浜田さんが奇しくも「人は人で育つ。小さいうちから大勢の大人の人と関わる必要があるのではないか!?」と仰った事は、現代の状況(子どもの核化)から鑑みても理にかなった意見と思いました。 『続ける為には・・』 また、藤木会長は「続ける事が一番難しい」といわれ、プレイパークが今まで続いている理由として「分担しない」「制約しない」「楽しいから関わる」等を基本スタンスとして挙げられました。そしてそれを補足するかのように、井上自治会長が「ボランティアをやりたい方は地域には必ずいる。その方を見つけ出すのが一番大切だし、一番難しい」と仰いました。 地域に埋もれているボランティア探しのヒントとして思ったのは、井上自治会長と藤木会長の出会いのエピソードでしょうか。 「熊本市主催の『町作り講習会』が何度も開かれたが、そこには必ず藤木会長とやまなみ保育園・山崎園長のお二人の姿が必ずあった」(井上会長)。 結局このお二人が長嶺・プレイパークの主要メンバーとなっていった経過を考えると、行政主導の町作りの研修会を通して、人材発掘を行うやり方もあるのだな、という事でしした。 質疑等が終わった後は昼食となりました。昼食は、敬愛保育園の先生に作っていただいたケーキとサンドイッチを頂きながら、おいしくプレイパークで食事が出来ました。 研修も昼食も、とても気持ちのいい、心の暖かい実地研修会となりました。 午後:「やまなみ保育園にてワークショップ」 最初に浜崎教授より、午後の部の導入という意味でも「支援センターの今後の課題」等についてお話をいただきました。 『センターの3つの側面』 浜崎教授 支援センターは『総合的に支援する』、と言う。しかし、この『総合的』というのが曲者でよくわからない。 プレイパークはそういう意味で、いい場所だったなと思う。地域に根ざしたプレイパークだった。熊本市には12箇所ある。しかし、常設施設は長嶺プレイパークのみ。そして「自分の責任で遊ぶ」という場所。 子育て支援には3つの側面(支援)がある。「一、子ども」・「二、親」・「三、地域」がある。「今の状況では、私はどういう形で携われているだろうか?」というセンター職員の認識が必要。 以前は「地域」ということが支援しなくても存在していた。それが経済成長と共に崩れて(核家族化等)、その結果細分化され3つの支援が出てきた、と言える。 長嶺は新興住宅地であるがゆえに地域を再生してきた、ともいえる。地域つくりの発展段階にある。熊本市の場合、行政と地域の連携が比較的うまくいっている。行政だけでは難しいし、地域だけでも難しい。行政が適度に関わりながら、基本的に地域に任せていくということが大切になってくる。 長嶺プレイパークは自分達で、手作りで一つずつ作っていった。協力し合いながら、そしてその後に懇親会をしながら自分達で「場」を作っていった。そして難しいのが、維持・継続ということだ。その反対の方向で、解体と言う事もありえるからだ。 3つの側面と言ったが、それぞれが単独で存在するのではなく交互に絡み合うという事を考えていきたい。 『ワークショップ』 その後、熱心にグループワークが各班に分かれて討論され、そして発表となりました。 個人的に耳に残った発表の一言は「その地域を愛しているものが・・・」という一言でしょうか。仕事云々ということもありますが、地域が好きかどうか?!ということは、地域への「情熱」という意味でも、やはり、最後のスパイスになるのだろうと思いました。 最後に、本日の研修の場をお世話いただいたお二方にお話をいただき、浜崎教授より今回の研修で見えてきた『支援センターの課題』について提言をいただきました。 『連携とは』 やまなみ保育園・山崎園長 今まで出てこなかった方だったが、藤木さんはいい人材だった。その証拠にあっという間に応援団が集まった。 今までとは違う視点で事業が進展したと思う。『こういうことをやりたいから、山崎先生来て』と言われればそういうときは行きます。これが連携だと思う。 危険を察知して、遊べる子どもを育てたい。その事を施設長として腹に据えて、プレイパークには子ども達を連れて行きます。 親子で遊ぼう会の時には、「食育の会」のメンバーに来ていただいて、炊き出し等をやってもらっている。色々な団体で、連携をとりながらやっている。地道なつながりの中で、2人3人と増やしていくようにしているが、息切れしないように、無理をしないようにやっていくことが大事だと思っています。 『目指すべき社会とは』 藤木会長 昼寝をしながら、子ども達を遊ばせている。昼食時には昼飯を作ってやる。常連の子ども達が来てくれる。来てくれる人たちの小さな居場所を作っている、と思っている。 私は『魂の開放』と呼んでいるが、『包容力のある社会』を目指していきたいと思っている。 『センター職員の課題とは』 浜崎教授 自分は地域子育てコーディネーターとして、どういう関わりが出来るか?を具体的に考えなければならない。「私に何が出来るか?」だ。 全体のコーディネートに対して、この会で答えが出るはずはない。が、「これは出来るが、これは課題だ」と言う事を明確にするのが、重要ではないか。 3つの視点(子どもの発達、親の発達、地域の発展)の中で、子どもの発達はプロだが、親育ちの支援は最近出てきた課題である。が、地域をコーディネートしようと思うと、地域に出なければいけない。施設にいてもダメだ。「我々は子どものプロではあるが、親や地域に関してはプロではない」という自覚が大切になってくる。 プレイパークの中には、子ども支援は当然あるが、親への関わり(連携や情報交換など)も当然出てくると思う。親が関わると言う事は当然「地域」作りが形成されてくる。そうなると当然プレイパークの役割が増えてくるということだ。 しかし、熊本市にあるプレイパークの殆どはイベント型であり、上記の営みは難しい。そういう意味でも常設型が望ましい。 保育所の役割もそうだ。現代の流れはプレイパークのように親への関わり、地域つくりを役割として求められている。プロと言うなら、それなりの知識が当然求められてくる。 「私はわからん」というのはある意味正直な感想だと思う。であるからこそ、その葛藤をくぐって、もがく必要があると思う。 出来るところから整理して、「今私に何が出来るか」を考えなければならない。 子育て支援が10年目を迎えて、一つの大きな岐路に立っていることが浜崎教授の話からも伺えました。 「支援とは何か?」という根本的なものが、今見直さなければならない案件であることが、長嶺・プレイパークの営みを通してまた一つはっきりしてきたように感じます。 研修者は現場に立ち、直接肌でその難しさを感じていることだと思います。であるからこそ、歯を食いしばって今そのことに向かい合い、自らの手で新しい支援センターの方向性を、新たな視点のもと確立していただきたいと願わずにはおれませんでした。 |
|
| (文責:子育てネット運営委員 橘 孝昭) |
(C)熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会(熊本子育てネット)All RightReserved