![]()
| 日 時 | 平成18年12月 5日 | |
| 午前の部 | ○開講 あいあつ 本日の進め方 ○評価項目の話し合い ○ノウハウの出し合い ○発表 |
|
| 午後の部 | ○自分の振り返りとこれからのスタート ○私のコーディネーター宣言! ○まとめ 修了証授与 記念撮影 |
 |
 |
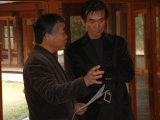 |
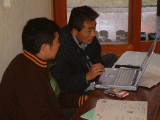 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
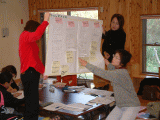 |
 |
 |
 |
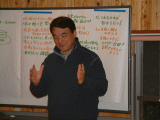 |
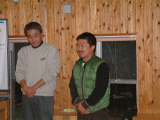 |
| 第4回 コーディネーター研修会報告 |
|
| 於: 雑草の森 | |
| 討議 〜ワークショップ・「子」「親」「地域」のどこに力点を置くのか〜 「子」0人 「親」17人 「地域」8人 〜に 偏ってしまう 3つに分けることへの戸惑い(参加者より発言)。議論あり。 子9人 親9人 地域7人 〜 に変化する 発表 子ども支援 の部 子どもの心身の発達 思春期を見通して子どもの発達を捕らえている 生活環境の把握 ニーズの把握 知識情報 親支援の部 居場所作り アドバイス(押し付けでない) 地域支援の部 実態ニーズの把握 人材を引き出す力 交流出来る場作り 連携 自分自身が積極的に参加する 情報の発信 浜崎先生から 基本的に抑えなければならない視点が欠けていないかどうかをチェックしなければならない。 今回の評価項目は、自分がどう捉えているのか、そこから出てきていると思う。 「これからのスタート」 〜私のコーディネーター宣言〜 出会いの場を作りたい ・ 近所の物知りおばさんでありたい ・ 支援センターとしてだけでなく地域の一員としてやっていきたい ・ ボランティアの人に勝手に期待をしないで出会いを大事にしたい ・ 家庭訪問をやってみたい ・ 地域の事はあまり知らなかった事に気づいた ・ 不安な人が多いので他の機関と協力しないと対応できない ・ 地域の行事に参加していきたい ・ 地域のひとや場所を知り、ひとつひとつを丁寧につなげていきたい ・ 共通の思いを持った人を探し出してつながりあっていきたい ・ 情報の宝箱になりたい ・ 人と話すのが苦手なので(それを隠す為に)押し付けの支援をやっていなかったかな?と反省した ・ 何かしなければならないという頭が離れる事が出来なかったがみんなで考える事をしていきたい ・ 出来るという自身をつけていきたい ・ 保育所とセンターは違うということがよくわかった ・ 人と人との繋がりは多くなったが、広がりがなくなった気がする。しかし、ここで勉強すると広がらなければならない、広げたいと思うようになった ・ センターや集いは出来てきたが、横のつながりの不足を感じている ・ 行政にいるので、子育ての地域資源を知っているのが強みだと思っている ・ 子育て資源のガイドブックを作っている ・ 自分に足りない面が多すぎるので、学びを深めていきたい ・ 色々な場所に出かけていって顔を覚えてもらうようにしている。エプロンは外さないようにしている。覚えてもらえるために。色々なところで支援センターの役割を伝えていきたい ・ 保育所でセンターをやっているので他の保育園や機関との連携がないように感じている。自分のところだけで計画を立てているような気がする ・ 子育て通信を持って家庭訪問をしている 押し付けて支援やアドバイスをしていた気がする ・ 話をする中で色々と支援を考えていきたい ・ 暖かい無関心というのも必要ではないか、と考えている ・ 出来る限り先入観を持たず、自分の感性で聞いていきたい ・ 話し方や言い方をもっともっと学びたい ・ 相手に学ぶ姿勢を大切にしたい 今年の研修を受けた感想 ● 得意な分野、そうでない事がわかった。そして、色々な地域の活動がわかった。 ● 難しかったけど、皆さんと出会えてよかった。 ● 難しかったけど、これを足がかりにしてやっていきたい ● コーディネーターの仕事が見えてきた気がする ● センターは何かな?という段階で勉強して、自分なりにがんばって行きたい ● 今まで以上に細やかな対応が出来るような気がする ● 自分が考えて学ぶスタイルだったので、難しかったけど後で楽しくなった ● 支援センターには別の役割があることを知った ● いかに自分に出来てない事がわかった。コーディネーターは一人ではない。 一人ではコーディネーターは出来ない ● 自分が本当に支援者でいいのかな、と思った。コーディネーターは難しい ● 他の支援のあり方を見て、自分のセンターのあり方を振り返る事が出来た ● 漠然としていたが、保育士はこれまで以上に専門性と他の機関との連携を 持つ必要を感じた ● 理解が難しかったが、4人で参加したので帰りにお互いに確認しあう事が 出来た ● 他の支援センターの人と話し合う場が宿題を通して出来た気がする ● ばあちゃんちは目からうろこだった。 ● 職員一人一人と話し合いながら進めていきたい。人と場所を選びながら話を 進めていきたい。毎回違う場所で、違う食事が楽しみだった。こういう研修会 が出来るような発想が出来るようにしていきたいと思った。こういうことが あったよ、と他の先生方と誘い合ってやってみたいと思った ● 現場に行って保育が食や農とつながっている事がわかった。長嶺では意外な ところに資源があることを知った。地元を見直すきっかけになった ● 漠然としていた支援センターが、自分なりにわかるようになってきた。 出してくれた園に感謝したい ● 4回ともこだわりがあった。場所がわからずあせった事を覚えている。 ● 4回とも下見に行った。人の意見を聞く機会が出来たので、園に帰って 園長や主任に報告し今後につなげていきたい ● 4回ともユニークな研修会でした。参加するたびに地元と重ね合わせながら 考えていた気がする ● 自分にしか出来ない何かとは何か、ということを見つけるための見通しを 考える場になった ● 色々な人の意見が聞くことが出来た 浜崎先生より 〜4回の研修を受けて〜 1、サポートグラフを持って精度の高いことをやっていただきたい。自分の強み、弱みを把握していただきたい。 2、家族支援・親支援は難しい。閉じてしまっているから、把握が出来ないでいる。子育て相談に来られるその殆どが良い母親・父親を自負する人がいる。家庭を把握する、ということはかなり難しいものになっているから、精度の高い専門性を磨いて欲しい。客観的に判断できるような材料が必要になるだろう。 3、今年の研修は共通の話題があって、やりやすかったと思う。しかし、地域は見たくとも見るのは難しい。地域を把握するとはどういうことか、を考えなければならない。私の思い描く地域は昔の地域だ。それは既に崩壊した。かつての地域とは「みんなの場所」だった。共有空間だった。 ウチの地域にはみんなが出入りできるような共有空間があるかどうか。なければ作らなければならない。家庭の中にも共有空間を作るようにしなければならない。 4、行政とのパートナーシップは広がりを持つ為に必要な存在。広報力と信用力を手に入れる事が出来る。 自分の課題を見つけて見通しを立てなければならない。 |
|
| 以上文責:子育てネット運営委員 橘 孝昭 |
(C)熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会(熊本子育てネット)All RightReserved