![]()
| 日 時 | 平成18年8月 2日 | |
| 午前の部 | 「親になるとは} ○開校式 ・会長あいさつ ・玉名市からの歓迎のあいさつ ・本日の進め方 ○養成講座全体の進め方(浜崎先生 ○リングペローについて(藤森由美さん) ○リングペローについての方がたから ○自由討議 |
|
| 午後の部 | 「親になるとは?」ワークショッッププログラム ■ステップ1:班分けとテーブル配置 ■ステップ2:自己紹介 ■ステップ3:○○さん親成り物語 ■ステップ4:親が求めている支えとは? ■ステップ5:各班発表 ■ステップ6:全体での意見交換 |
|
|
夏の日差しが照りつけ、あの悪夢のような集中豪雨の後とは思えないほど良く晴れ渡った青空の下、第2回地域子育て支援コーディネーター養成講座『親になるとは?』が玉名市高瀬・高瀬蔵にて行われました。 午前10時に地元・玉名市の福祉課課長からご挨拶を頂き開講式が始まりました。 続いて尚絅短期大学の浜崎教授より「養成講座全体の進め方」と題して、前回の感想文等を踏まえた上で留意する点、そしてこれからのコーディネーター養成講座に必要な視点等についてお話をいただきました。熱心に聞き入る参加者の姿から、自身の地域への子育て支援に賭ける意気込みが伝わりました。 続いて本日のメイン・ゲストとしてお越しをいただきました子育て交流サークル・「リングペロー」のメンバーの方3人(A、B、Cと以下標記)と、玉名市保健センター保健師・藤森 由美先生に正面に立っていただきました。 簡単な自己紹介の後、藤森先生の司会の下三人のメンバーにそれぞれの自己経験を中心にして話はすすみました。 「…高校も卒業していない、社会も知らない、周りのお母さんに合わせるべく背伸びをしてお付き合いをしなければならないこの10代の若いお母さん方が、どの様にして目の前の不安と立ち向かっていったか。他にもメンバーはいらっしゃいますけど、本日はこのメンバーの方に自身の経験について語っていただきたいと思います。」 『妊娠がわかった時・・・』 A:びっくりしたが、嬉しかった。パートナー(現主人)は戸惑っていた様子だった。当時私は専門学校在学中で、学生だった。父は理解があったが、母が(事実を)受け入れるのが難しかったようだ。母は、私が期待を裏切ったように感じていたようだった。妊娠中は外出がしにくかった。 B:嬉しかった。育った環境が少々複雑な環境だったので、結婚願望が強かった。主人にも迷いはなかった。義理の両親も積極的に支援してくれ、生まないという選択肢は私にはなかった。 C:嬉しかったが不安があった。母に相談すると「彼に相談を」と言ってくれた。 『妊娠中に嬉しかった事、つらかった事・・・』 A:嬉しかった事 ・ 父と母が分娩室に聞こえるくらい大きな声で「バンザイ!」を言ってくれたこと。 ・ 病院の産後訪問が有難かった。悩みを全部聞いてくれた。その後町の保健師さんの訪問の時「何かあったら連絡してね」と言われた時。(回りや近所に文句を言わせないために頑張っていた時だったから嬉しかった) つらかった事 ・ 外出した時「(自分が出たいから)いつも連れ回しているんだろ」と言われたり、思われた時 ・ 近所のヒソヒソ話が気になる時 ・ 夜に叱ったりして、子どもが泣いてしまった翌日に「泣かせよったね」と近所の方に言われた時 B:嬉しかった事 ・ 第一子を流産した時、義母に優しく声を掛けてもらった時 つらかった事 ・ 陣痛がきつかった ・ 流産した後は慎重になりすぎて、車に乗るのも怖くなってしまったこと。 C:嬉しかった事 ・ 妊娠中に子どもを育てる喜びを感じた つらかった事 ・ 妊娠中はつらい事はなかった。しかし、産院のスタッフに冷たく当たられた。出産後3日間子どもに会わせてくれずに、約3ヶ月ほど精神的に不安定になっていった。藤森さんの家庭訪問で話を色々聞いてくれて、ようやく外(子育てサークル)に出かけていこうという気になった。 『出産後の家庭の様子は・・・』 A:主人は出産後色々と手伝ってくれたが、徐々にそうではなくなっていった。しかし、子どもが大きくなるに連れ子ども中心になってくれた。両方の両親がとてもよくしてくれた。 B:主人はおっかなびっくりで、あまり関わろうとしてくれなかった。大きくなるにつれ段々関わってくれる様になってきた。 C:主人も含めて両方の親も子ども好き。 『幼稚園に行きだして・・・』 3人とも多少の違いはあるものの、おおむね幼稚園にやることを前向きに受け止めようとしている様子。 『仕事をやりだして・・・』 三人のうち二人のお母さんが同居。同居ではないお母さんが最近働きに出始められた。そのお母さんに聞いてみる。 夜のカラオケ店に勤めだした。昼間は子どもと接していたいので、「それだったら夜の仕事でもいいのではないか」と主人から提案があった。 当時引越しと幼稚園と色々重なってしまったので、4歳になる息子が1週間お漏らしが続いた。周囲から「子どもがいるのに大丈夫?」と言われたがその分、2番目の子どもに一生懸命接しようと思っている。子どもも「お仕事いってらっしゃい」と言ってくれるし、仕事先の同僚は理解があるので自分のリフレッシュにもなっている。夜に仕事をするのも悪くないか、とも思っている。 母親の夜の仕事は一般受けが悪い。しかし、父親が夜に仕事をするのは受け入れられる。だから、仕事を始めた当初は隠しておきたかった。 『一番かけて欲しい言葉は・・・』 ・ 出産時の痛みについて共感はしていただけるけれども、それよりも妊娠がわかった時や、その期間中の「生む」と決めた気持ちそのものを褒めて欲しかった。批判されたことが耳に入ると身体がこわばってしまう。心を開くことができない。何気ない言葉が気になってしまう。 ・ 父親(主人)に声を掛けて欲しい。そして、地域に引っ張り出して欲しい。母親は、母親同士のつながりや子育てについても考えることがあるが、父親はなかなかそういう機会がない ・ 市営住宅などでは、若い夫婦宅と老人宅とを向かい合わせに交互に住まわして欲しい。お互い協力(ゴミ出しを手伝う代わりに、ちょっとの間子どもを見てもらうなど)し合いながら住むことが出来るのではないか。お互いメリットはあると思う。 質問の時間にはリングペローのお母さんが「次は女の子を授かりたいけど、男系家族だから・・・」とフト漏らしたことについて、研修者から昔の体験談を披露して温かなアドバイスをしてくれました。自身の体験として、出産が男の子で続いたことについての周囲からのプレッシャーや、「次こそは・・・」という自分の意気込みが空振りにおわってしまった事等・・・。そして、会場は優しい雰囲気に包まれました。 誰もが頭ではわかっているという「自分ではどうしようもない」という問題であるからこその発言であり、先輩お母さんとして後輩お母さんへの必要な、優しい声かけだったと思います。人としてどうしようもない哀しみや切なさ、それを包み込むような研修者たちの温かな雰囲気でした。 子育て支援ウンヌンは別としても、人が人である以上どうしようもない、というそういうところを大切にし、理解し、受け止める、とても大切な発言だと聞いていて感じました。 最後に今回の研修会で橋渡し等の支援を頂き、「リング・ペロー」の最大の支援者・理解者の一人でもある、玉名市保健センターの 藤森 由美 先生の感じられた点を紹介致します。 『10代の親たちと関わりのなかで私が感じたこと』 (支援者は、批判的なところからみてしまうことが多いのでは?) 支援者の中には「10代の出産は問題である」という意識で関わりが始まったり、妊娠経過・出産・子育てのリスク管理や指導に視点が向いている(確かにその視点は必要と思うが)。しかし、それが若い親たちと支援者がつながりにくい、距離がある関係なのかなと思った。そこで、産む決心をした10代の女性の前向きな意志と、その事実をまず受け止めることから始めてみよう、と思った。 (どんな気持ちで妊娠、出産に向き合い、どんな思いで子育てをしているか?) 妊娠、出産、子育てと大きく自分の人生が変化していくことに右往左往している。 しばらく経過して、今までの自分を振り返り、そのときの自分に起こった出来事やそのときの気持ちをもう一度確認していくことで、次の自分を考えていけるのでは・・・と思っている。 良かった体験も含め、辛かった・きつかった・悲しかった体験などをこれからの自分の自信につながるような、自分自身との向き合い方を気づいて欲しい。 (支援していくことで母親の変化(成長)していく姿があった) 育児を媒体として支援していくことで、親たちが「親としての人生を歩む」ことを気付く・考えていけるような関わりをしていきたいと思う。 若いお母さんと聞いていましたが、とても落ち着いた口調で聞きやすく、精神的にも大人の雰囲気が窺えました。そして若くても、お互いの両親を含めた温かな人と人とのつながりがあれば何とかやっていけるのだな、ということがよく窺えました。 現代は少子化が叫ばれ、その対策についてあれこれと論じられていますが、特別なことではなく何度でも足元にある人としての幸せを、我々自身もっと再確認していけば道が開けるような気がした研修会でした。
|
||
 |
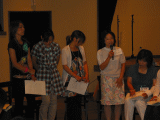 |
 |
 |
 |
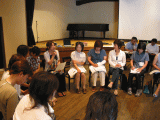 |
 |
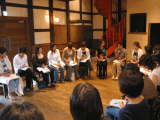 |
(C)熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会(熊本子育てネット)All RightReserved